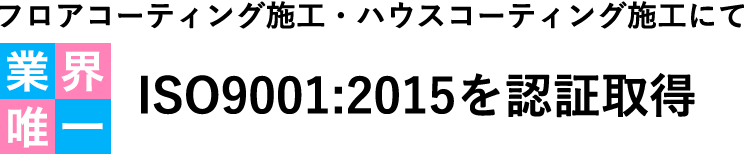- フロアコーティングのハートフルコート
- コラム
- 【床の傷、自分で直せる!】フローリングの補修方法を徹底解説!費用も抑えるDIY術
【床の傷、自分で直せる!】フローリングの補修方法を徹底解説!費用も抑えるDIY術
- 2025.04.18 (金)
「あ、また床に傷が…」
小さなお子さんやペットがいるご家庭、または賃貸物件にお住まいの方なら、床の傷は悩みの種ですよね。でも、大丈夫!
実は、床の傷は自分で簡単に補修できるんです。
この記事では、フローリングの傷の種類別の補修方法から、必要な道具、費用を抑えるコツまで、DIY初心者の方でも分かりやすく解説します。賃貸物件にお住まいの方でも安心な補修方法もご紹介します。
この記事を読めば、あなたも床の傷を自分で補修できるようになり、費用を節約し、お部屋をきれいに保つことができるでしょう!
1. 床の傷の種類を知ろう
「あ、また床に傷が…」
小さなお子さんやペットがいるご家庭、または賃貸物件にお住まいの方なら、床の傷は悩みの種ですよね。でも、大丈夫!
実は、床の傷は自分で簡単に補修できるんです。
この記事では、フローリングの傷の種類別の補修方法から、必要な道具、費用を抑えるコツまで、DIY初心者の方でも分かりやすく解説します。賃貸物件にお住まいの方でも安心な補修方法もご紹介します。
この記事を読めば、あなたも床の傷を自分で補修できるようになり、費用を節約し、お部屋をきれいに保つことができるでしょう!
1-1. 表面の引っかき傷
床の表面に浅く付いた引っかき傷は、日常的に最もよく見られる傷の一つです。物を落としたり、椅子を引きずったりすることで発生します。これらの傷は、比較的簡単に補修できる場合が多いです。
1-2. へこみ傷
重い物を落としたり、家具の脚が床に強く当たったりすることでできるへこみ傷。深いものになると、見た目にも影響を与え、補修にも手間がかかることがあります。
1-3. 剥がれ・えぐれ傷
床材の表面が剥がれたり、えぐれたりするような深い傷です。物をぶつけたり、カッターなどの鋭利なもので傷つけたりすることで発生します。このタイプの傷は、補修に専門的な技術や材料が必要になることもあります。
これらの傷の種類を理解することで、適切な補修方法を選択し、より効果的に床の美観を回復させることができます。
2. 傷の種類別の補修方法
2-1. 引っかき傷の補修方法
引っかき傷は、フローリングの傷の中でも比較的軽度で、DIYでの補修がしやすい種類です。補修方法は、傷の深さや範囲によって異なりますが、基本的には以下の手順で進めます。
まず、傷の周りの汚れをきれいに拭き取ります。次に、傷を目立たなくする補修材を選びます。クレヨンタイプ、ペンタイプ、補修液タイプなど、様々な種類がありますので、傷の色やフローリングの色に合わせて選びましょう。傷に補修材を塗り、乾いたら余分な部分を拭き取って完成です。必要に応じて、研磨ペーパーで表面を滑らかに整え、ワックスを塗布すると、より自然な仕上がりになります。
2-2. へこみ傷の補修方法
へこみ傷は、重い物を落としたり、家具を引きずったりすることで発生します。このタイプの傷は、引っかき傷よりも補修に手間がかかる場合があります。補修方法は、以下の通りです。
まず、へこみ部分に濡れた布を当て、上からアイロンをかけます。こうすることで、木材が水分を吸収し、膨張してへこみが浅くなることがあります。へこみが深い場合は、パテを使って補修します。パテをへこみ部分に埋め込み、ヘラで平らにします。乾燥後、サンドペーパーで研磨し、表面を滑らかに整えます。最後に、補修箇所に着色し、ワックスを塗って仕上げます。パテの色選びが重要で、フローリングの色に近いものを選ぶと、補修跡が目立ちにくくなります。
2-3. 剥がれ・えぐれ傷の補修方法
剥がれやえぐれ傷は、床材が大きく損傷している状態です。この場合、部分的な補修では対応できないこともあります。補修方法としては、まず傷ついた部分を取り除き、新しい床材を埋め込む方法が一般的です。
傷の部分をカッターなどで丁寧に切り取り、同じサイズの新しい床材をはめ込みます。隙間なくぴったりと収まるように調整し、接着剤で固定します。最後に、表面を研磨し、着色、ワックスを塗布して仕上げます。この作業は難易度が高く、DIYでの補修が難しい場合は、専門業者に依頼することも検討しましょう。部分補修用の補修材や、傷を隠すためのリペアペンなども市販されていますので、状況に応じて使い分けると良いでしょう。
3. 補修に必要な道具と材料
DIYでの床の傷補修を始めるにあたって、どのような道具や材料が必要になるのでしょうか。ここでは、補修の際に必要となる主な道具と材料について、詳しく解説していきます。
3-1. 補修キット
補修キットは、床の傷補修に必要な道具と材料がセットになっている便利なアイテムです。初心者の方でも手軽に補修を始められるように、必要なものが一通り揃っています。引っかき傷や小さなへこみ傷など、軽度の傷の補修に適しています。
補修キットには、補修ペン、パテ、ヘラ、サンドペーパー、ワックスなどが含まれています。傷の種類や程度に合わせて、適切なキットを選ぶことが重要です。ホームセンターやオンラインショップで購入できます。
3-2. パテ
パテは、床のへこみ傷やえぐれ傷を補修する際に使用する充填剤です。傷の部分にパテを埋め込み、表面を平らにすることで、傷を目立たなくすることができます。パテには、木部用、フローリング用、クッションフロア用など、様々な種類があります。床材の種類に合わせて、適切なパテを選びましょう。
パテの色は、フローリングの色に近いものを選ぶことが重要です。乾燥後、サンドペーパーで研磨し、表面を滑らかに整えます。パテの種類によっては、硬化剤を混ぜて使用するものもあります。使用方法をよく読んでから使いましょう。
3-3. ヤスリ
ヤスリは、補修箇所の表面を研磨し、平らにするために使用します。サンドペーパーとも呼ばれます。目の粗さによって、仕上げの度合いを調整できます。補修後の表面を滑らかにするために、細かい目のサンドペーパーを使用します。また、パテを研磨する際にも使用します。ヤスリがけは、補修の仕上がりを左右する重要な工程です。
3-4. 塗料
塗料は、補修した部分の色を調整するために使用します。フローリングの色に合わせて、着色塗料やリペアマーカーを選びましょう。傷の範囲が広い場合は、刷毛や筆を使って塗料を塗布します。小さな傷の場合は、リペアマーカーで部分的に補修することも可能です。塗料を塗布する際は、周囲の色とのバランスを見ながら、慎重に行いましょう。
3-5. ヘラ
ヘラは、パテを塗布する際に使用します。パテを傷に埋め込み、表面を平らにする際に役立ちます。ヘラには、金属製、プラスチック製など、様々な種類があります。パテの種類や用途に合わせて、適切なヘラを選びましょう。ヘラを使うことで、パテを均一に塗布し、滑らかな仕上がりを実現できます。
4. 費用を抑える!100均グッズ活用術
4-1. 100均グッズの種類
100円ショップには、床の傷補修に役立つ様々なグッズが揃っています。例えば、補修用のクレヨンやペン、パテ、研磨材、ヘラなどがあります。これらのグッズを上手に活用することで、費用を抑えながら、床の傷を補修することができます。
4-2. 100均グッズを使った補修方法
4-2-1. 引っかき傷の補修
引っかき傷には、補修用のクレヨンやペンがおすすめです。傷の色に合わせてクレヨンやペンを選び、傷の部分に塗り込みます。乾いたら、余分な部分を拭き取り、完成です。
4-2-2. へこみ傷の補修
へこみ傷には、パテが有効です。100円ショップで販売されている木部用のパテを選び、へこみ部分に埋め込みます。ヘラで表面を平らにし、乾燥後、サンドペーパーで研磨して仕上げます。
4-2-3. その他のグッズ活用
その他、研磨用のサンドペーパーや、ヘラなども100円ショップで手軽に手に入れることができます。これらのグッズを組み合わせることで、様々な床の傷に対応できます。
4-3. 注意点
100均グッズは、手軽に入手できる反面、耐久性や仕上がりのクオリティは、プロ用のものに劣る場合があります。また、賃貸物件では、原状回復義務があるため、補修方法によっては、退去時に追加費用が発生する可能性があります。補修を行う前に、必ず賃貸契約書を確認し、大家さんや管理会社に相談することをおすすめします。
5. 賃貸物件での補修の注意点
賃貸物件での床の傷補修は、持ち家の場合とは異なる注意点があります。退去時の原状回復義務や、補修方法によっては費用が発生する可能性も考慮しなければなりません。ここでは、賃貸物件での補修における注意点について詳しく解説します。
5-1. 原状回復義務とは
賃貸物件を借りる際には、契約書に「原状回復義務」という条項が含まれていることが一般的です。これは、借り主が故意または過失によって物件を損傷させた場合、退去時に元の状態に戻す義務があるというものです。床の傷も、この原状回復義務の対象となる場合があります。
5-2. どこまでが原状回復の範囲?
原状回復の範囲は、傷の種類や程度、契約内容によって異なります。一般的には、通常の使用によって生じた傷(通常損耗)は、賃貸人が負担することになります。しかし、故意に傷つけた場合や、通常の使用を超えた傷(過失による損傷)は、借り主が費用を負担することになる可能性が高いです。
5-3. 賃貸契約書の確認
賃貸物件の補修を行う前に、必ず賃貸契約書を確認しましょう。契約書には、原状回復に関する詳細な規定や、退去時の修繕費用の負担に関する取り決めが記載されています。特に、床の傷の補修に関する具体的な記述がある場合は、それに従う必要があります。
5-4. 事前の大家さん・管理会社への相談
補修を行う前に、大家さんや管理会社に相談することも重要です。補修方法や使用する材料について、事前に確認しておくと、退去時のトラブルを避けることができます。また、補修の許可を得ることで、安心してDIYに取り組むことができます。
5-5. 補修方法の選択
賃貸物件での補修方法は、慎重に選択する必要があります。退去時に原状回復が必要な場合、補修方法によっては追加費用が発生する可能性があります。そのため、できるだけ原状回復が容易な方法を選ぶことが重要です。例えば、補修キットやリペアペンなどを使用し、傷を目立たなくする程度にとどめるのが良いでしょう。大規模な補修が必要な場合は、専門業者に依頼することも検討しましょう。
5-6. 退去時の注意点
退去時には、必ず床の傷の状態を大家さんや管理会社に確認してもらいましょう。傷の程度や、原状回復の必要性について、事前に話し合っておくことで、退去時のトラブルを未然に防ぐことができます。また、補修を行った場合は、その内容を記録しておくと、後々の交渉に役立ちます。
6. 補修後のメンテナンス
床の傷を補修した後も、美しい状態を長く保つためには、適切なメンテナンスが不可欠です。日々のちょっとした心がけと、定期的なお手入れで、フローリングの寿命を延ばし、快適な住空間を維持することができます。
日常的なお手入れ
毎日の掃除は、床をきれいに保つための基本です。掃除機やフローリングワイパーを使って、こまめにホコリやゴミを取り除きましょう。特に、砂や小さなゴミは、床材を傷つける原因になるため、注意が必要です。掃除機を使用する際は、ヘッド部分をフローリングに優しく当て、傷つけないように注意しましょう。また、化学モップなどで拭き掃除をするのも効果的です。水拭きをする場合は、固く絞った雑巾を使用し、水分が残らないようにしましょう。
定期的なお手入れ
定期的なお手入れも、床の美しさを保つために重要です。ワックスがけは、床の表面を保護し、傷や汚れから守る効果があります。ワックスの種類によっては、耐久性や防汚性に優れているものもあります。ワックスがけを行う前に、床をきれいに清掃し、完全に乾燥させてから行いましょう。ワックスを塗布する際は、均一に薄く塗り広げ、乾燥時間を守ることが大切です。ワックスの種類や使用方法については、商品の説明書をよく読んでから行ってください。また、床材によっては、ワックスがけが不要なものもありますので、事前に確認しておきましょう。
傷防止対策
床の傷を予防することも、メンテナンスの一環として重要です。家具の脚には、保護パッドを取り付け、床への直接的な接触を避けましょう。椅子の場合は、脚にカバーを装着したり、カーペットやラグを敷くことで、床の傷を軽減できます。また、重いものを落としたり、引きずったりしないように注意しましょう。お子さんやペットがいる場合は、床に傷がつきやすい状況を考慮し、対策を講じることが大切です。
補修箇所のケア
補修した箇所は、特に丁寧にケアしましょう。補修材が完全に乾燥するまでは、触ったり、水拭きしたりしないように注意してください。また、補修箇所の色褪せを防ぐために、直射日光を避けるようにしましょう。補修した箇所が剥がれたり、傷ついたりした場合は、再度補修を行う必要があります。補修方法によっては、定期的なメンテナンスが必要になる場合もありますので、補修後の注意点についても、事前に確認しておきましょう。
まとめ
床の傷補修後のメンテナンスは、床の美観を維持し、寿命を延ばすために不可欠です。日々の掃除や定期的なお手入れ、傷防止対策を組み合わせることで、フローリングを長く美しく保つことができます。補修した箇所も丁寧にケアし、快適な住空間を維持しましょう。
7. まとめ
床の傷の補修方法について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
この記事では、フローリングの傷の種類、それぞれの補修方法、必要な道具や材料、費用を抑えるコツ、賃貸物件での注意点など、DIY初心者の方にも分かりやすく解説しました。
床の傷は、適切な方法で補修することで、見た目をきれいに保ち、お部屋の価値を維持することができます。DIYに挑戦することで、費用を節約できるだけでなく、達成感も味わえるでしょう。
もし、補修方法で迷ったり、より専門的なアドバイスが必要になった場合は、お気軽に専門業者にご相談ください。この記事が、あなたの床の傷補修のお役に立てれば幸いです。
1DAY 施工
期間限定キャンペーン実施中!
期間限定キャンペーンは、先着順での対象になりますので、お早めにお問い合わせください!
現地での訪問見積りも無料で実施中です!
24時間受付中のお申込みフォームから
お気軽にお問い合わせください!
お電話でのお問い合わせもお気軽に!
0120-292-444